社会人になって最初に任される業務のひとつが「電話対応」です。メールやチャットが普及している時代とはいえ、ビジネスにおいて電話は依然として重要なコミュニケーション手段です。しかし、新人にとって電話対応は特に緊張を伴う場面でもあります。相手の顔が見えないため、声や言葉遣いだけで印象が決まってしまい、少しの言い間違いや言葉の選び方が相手の不快感につながることもあります。
また、電話は即時の対応が求められるため、事前に考える余裕がなく、焦りから失敗してしまうことも少なくありません。ただし、失敗そのものは決して珍しいことではなく、改善策を知り意識して行動することで確実に克服できます。本記事では、新人がやりがちな電話対応の失敗を具体的に取り上げ、それぞれに適した改善策をご紹介いたします。
新人がやりがちな電話対応の失敗5選
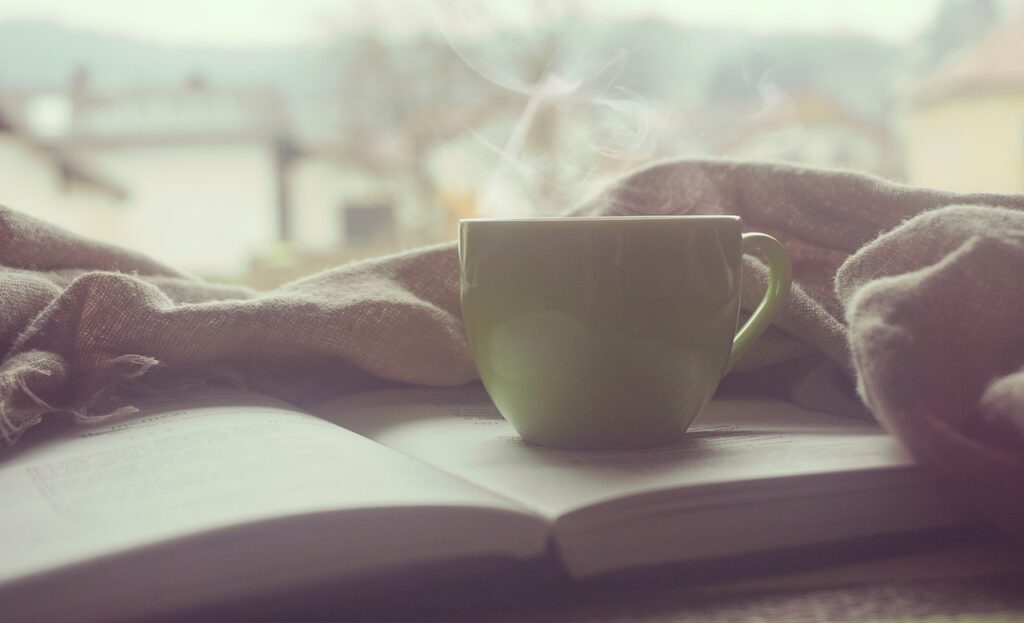
1. 名乗りが不明瞭で相手に伝わらない
電話を受けた際に「はい、○○です」と小さな声で答えてしまうと、相手には会社名や担当者名が伝わらず、不安を抱かせることになります。特に企業の代表電話では、最初の名乗りがそのまま会社全体の印象につながるため注意が必要です。
2. メモを取らずに内容を忘れてしまう
電話口で聞いた内容を記憶だけに頼ると、後から詳細を思い出せずに伝達ミスが発生します。新人にありがちなのは、相手の名前や日時、数字をうっかり聞き逃してしまうケースです。これにより「きちんと聞いていない」と信頼を損ねる可能性があります。
3. 敬語表現を誤って使ってしまう
新人が特につまずきやすいのが敬語です。「ご苦労様です」と言ってしまったり、「了解しました」と返答してしまったりすると、相手に失礼な印象を与えてしまうことがあります。丁寧に話しているつもりでも、適切な敬語を使えていないと評価を下げてしまいます。
4. 相手の話を遮ってしまう
相手が話している途中で「はい」「分かりました」と急いで返答してしまうことがあります。これは無意識のうちにしてしまいがちですが、相手の言葉を遮る形になり、不快感を与える原因となります。
5. トラブル時に慌てて不適切な言葉を使う
クレームや問い合わせの中で想定外の質問を受けると、焦りから「分かりません」「できません」と即答してしまう場合があります。こうした対応は冷たい印象を与え、顧客の怒りを増幅させることにつながります。
失敗を防ぐための改善策と実践ポイント

1. ハキハキと名乗り、第一声で印象を整える
電話を受けたら「お電話ありがとうございます。○○株式会社でございます」と会社名を明確に名乗りましょう。声は普段より少し高めにし、明るくはっきりと発音することで好印象を与えられます。電話の第一声はその後の会話全体に影響を及ぼすため、最初の一言にこそ集中すべきです。
2. メモを習慣化し、復唱で正確さを確認する
電話対応時には必ずメモを取り、相手が伝えた内容を繰り返し確認しましょう。例えば「○月○日の△時ということでよろしいでしょうか」と復唱することで、誤解を防ぎつつ相手にも安心感を与えられます。メモを取る習慣は業務効率を上げるだけでなく、自身の安心材料にもなります。
3. よく使う敬語フレーズを事前にストックしておく
「かしこまりました」「承知いたしました」「恐れ入りますが」といった定番フレーズを繰り返し練習しておくと、実際の場面で慌てずに言葉が出てきます。また、「ご苦労様です」は目上の人に使わない、「了解しました」は「承知しました」に言い換えるなど、間違えやすい敬語は特に意識して覚えておくと安心です。
4. 傾聴を意識し、相槌や復唱で安心感を与える
相手が話している間は最後まで聞き、適度に「はい」「承知いたしました」と相槌を打つことで、しっかり聞いているという姿勢を示せます。要点を整理して復唱することも、相手に信頼感を与える効果があります。慌てて話を遮らず、落ち着いて聞く姿勢が大切です。
5. 困ったときは「確認のうえ折り返します」で冷静に対応
予想外の質問やトラブル対応では、無理にその場で答えようとする必要はありません。「ただいま確認いたしまして、折り返しご連絡差し上げます」と伝えることで、冷静かつ誠実な対応ができます。即答できないことを正直に伝える姿勢は、むしろ信頼につながります。
まとめ

新人が電話対応で失敗することは珍しくありません。しかし、失敗は改善のチャンスであり、意識して取り組めば必ず克服できます。
- 第一声は明るくハキハキと名乗る
- メモと復唱で正確に情報を伝える
- 敬語フレーズを事前に準備し誤用を防ぐ
- 相手の話を最後まで聞き、傾聴を意識する
- 困ったときは折り返し対応で冷静さを保つ
これらの改善策を日常的に実践することで、電話対応に自信が持てるようになり、顧客や取引先からの信頼も自然と高まります。電話は単なる連絡手段ではなく、信頼を築く第一歩です。失敗を恐れるのではなく、改善を重ねることで成長し、安心感を与える対応ができるようになっていくでしょう。
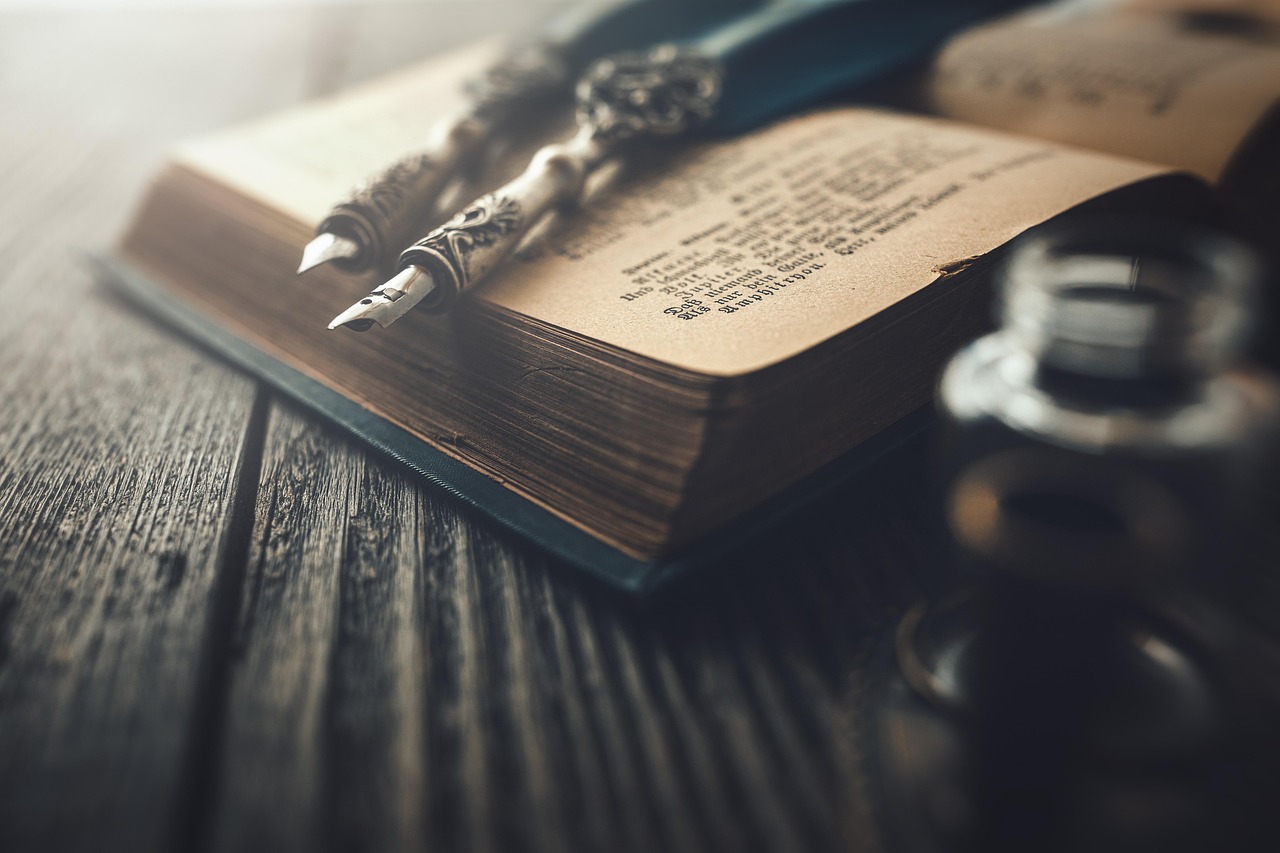


コメント