ビジネスにおいて、クレーム対応は避けて通れない重要な業務のひとつです。特に電話でのクレーム対応は、相手の表情や状況が見えないため、声や言葉遣いだけで印象が決まります。相手の感情がストレートに伝わるため、経験が少ない方にとっては「失敗したらどうしよう」という不安から緊張しやすい場面です。
さらに、電話は即時対応が求められるため、言葉選びに迷うと沈黙が生まれてしまい、相手に不信感を与えることもあります。こうした特性から「クレーム対応=緊張する」というイメージが強く根付いています。
しかし、緊張の多くは「準備不足」と「経験不足」から生まれるものです。基本的な姿勢や対応の流れを理解し、実践的な練習を積み重ねることで、落ち着いて対応できるようになります。本記事では、クレーム対応で意識すべき基本姿勢と、緊張を和らげるための実践的なコツを解説いたします。
クレーム対応で意識すべき基本姿勢

1. 傾聴と共感を重視する姿勢
クレーム対応の第一歩は「相手の話をしっかり聞く」ことです。相手の話を遮ったり、言い訳を挟んだりすると「理解してもらえていない」と感じさせ、怒りを増幅させてしまいます。
そのため、相槌を打ちながら最後まで傾聴し、必要に応じて「そのように感じられるのもごもっともでございます」と共感を示すことが大切です。共感を言葉にすることで、相手は「受け止めてもらえた」と感じ、気持ちが少しずつ落ち着いていきます。
2. 感情的にならず冷静さを保つ
相手が感情的になっているときに、対応する側も感情的になってしまっては解決に至りません。声のトーンを落ち着かせ、ゆっくりと話すことで安心感を与えることができます。
冷静さを維持するためには、返答の前に一呼吸置くことも有効です。即答が難しいときには「確認のうえ、折り返しご連絡いたします」と伝えることで時間を確保でき、誠実な印象を残せます。
3. 謝罪・確認・解決策提示の基本フロー
クレーム対応は「謝罪 → 事実確認 → 解決策提示」という流れを意識すると整理しやすくなります。
- 謝罪:「この度はご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございません」
- 事実確認:「具体的な状況をお伺いしてもよろしいでしょうか」
- 解決策提示:「再発防止に向け、改善に取り組んでまいります」
このフローを繰り返し習慣化することで、対応に迷いが生じにくくなります。
緊張を和らげるための実践的なコツ

1. 第一声を安定させる呼吸法と声のトーン
電話応対では第一声が印象を決めると言われています。呼吸が浅いと声が震えたり小さくなったりするため、腹式呼吸を意識して深く息を吸い、安定した声を出す練習をしておくと安心です。
声のトーンは普段より少し高めで、はっきりと発声することがポイントです。明るく落ち着いた声は相手に安心感を与え、緊張感を和らげる効果があります。
2. 台本やフレーズ集の活用で安心感を持つ
クレーム対応に備えて、よく使うフレーズをあらかじめ用意しておくと緊張が軽減されます。
例:
- 謝罪:「ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません」
- 保留依頼:「恐れ入りますが、確認のため少々お待ちいただけますでしょうか」
- 折り返し:「担当者が戻り次第、折り返しご連絡差し上げます」
定型フレーズを覚えておくと、言葉に詰まることが減り、余裕を持って対応できます。
3. メモと復唱で正確性を高める
緊張していると、相手の言葉を聞き逃したり内容を忘れたりすることがあります。そのため、必ずメモを取り、復唱を行うことが重要です。
「○月○日の△時にお伺いするということでよろしいでしょうか」と確認することで、誤解を防ぎつつ、相手に「丁寧に対応してもらえた」という安心感を与えられます。
4. ロールプレイや録音を活用した練習方法
実際の業務でクレーム対応をする前に、ロールプレイで練習を重ねることが効果的です。上司や同僚に協力してもらい、想定されるクレーム内容で練習をすると実戦感覚が養われます。
さらに、自分の対応を録音して聞き返すことで「声が小さい」「言葉が早口になっている」など改善点を客観的に把握できます。練習と振り返りを繰り返すことで、緊張に強くなり、自然に落ち着いた対応ができるようになります。
まとめ
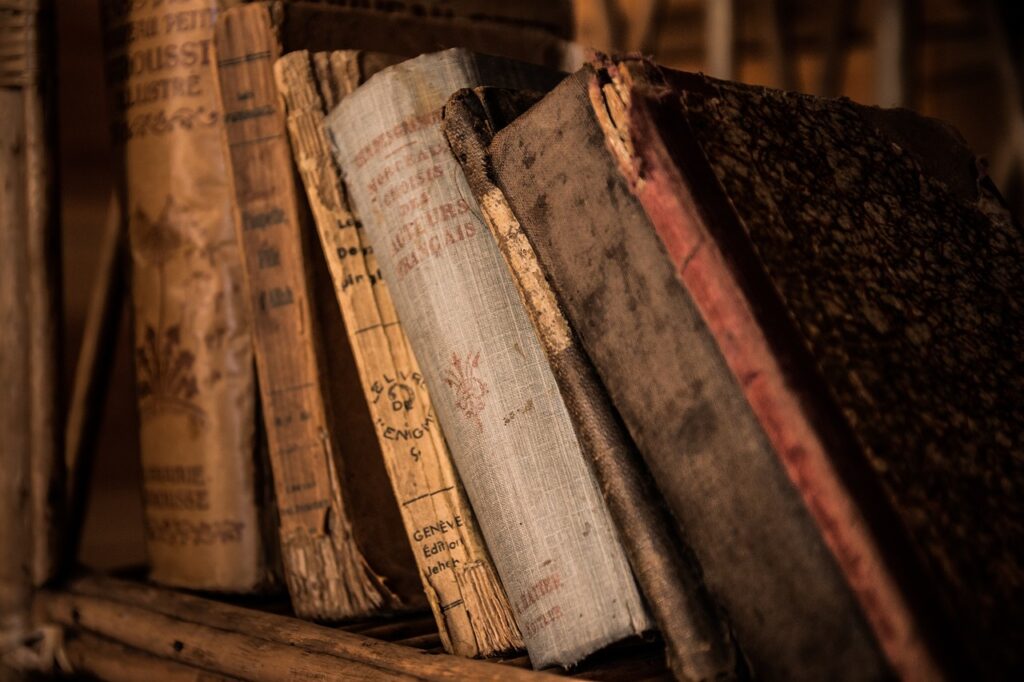
電話でのクレーム対応は緊張しやすいものですが、準備と習慣化によって克服することができます。
- 傾聴と共感で相手の感情を受け止める
- 冷静さを保ち、安心感を与える声で対応する
- 謝罪 → 確認 → 解決策提示の基本フローを守る
- 呼吸法・フレーズ集・復唱・ロールプレイを活用して緊張を和らげる
クレーム対応は一見負担の大きい業務に思えますが、誠実に取り組むことで信頼を獲得できる機会にもなります。落ち着いて対応する習慣を身につければ、緊張は徐々に克服され、安心と信頼を生む対応へとつながります。
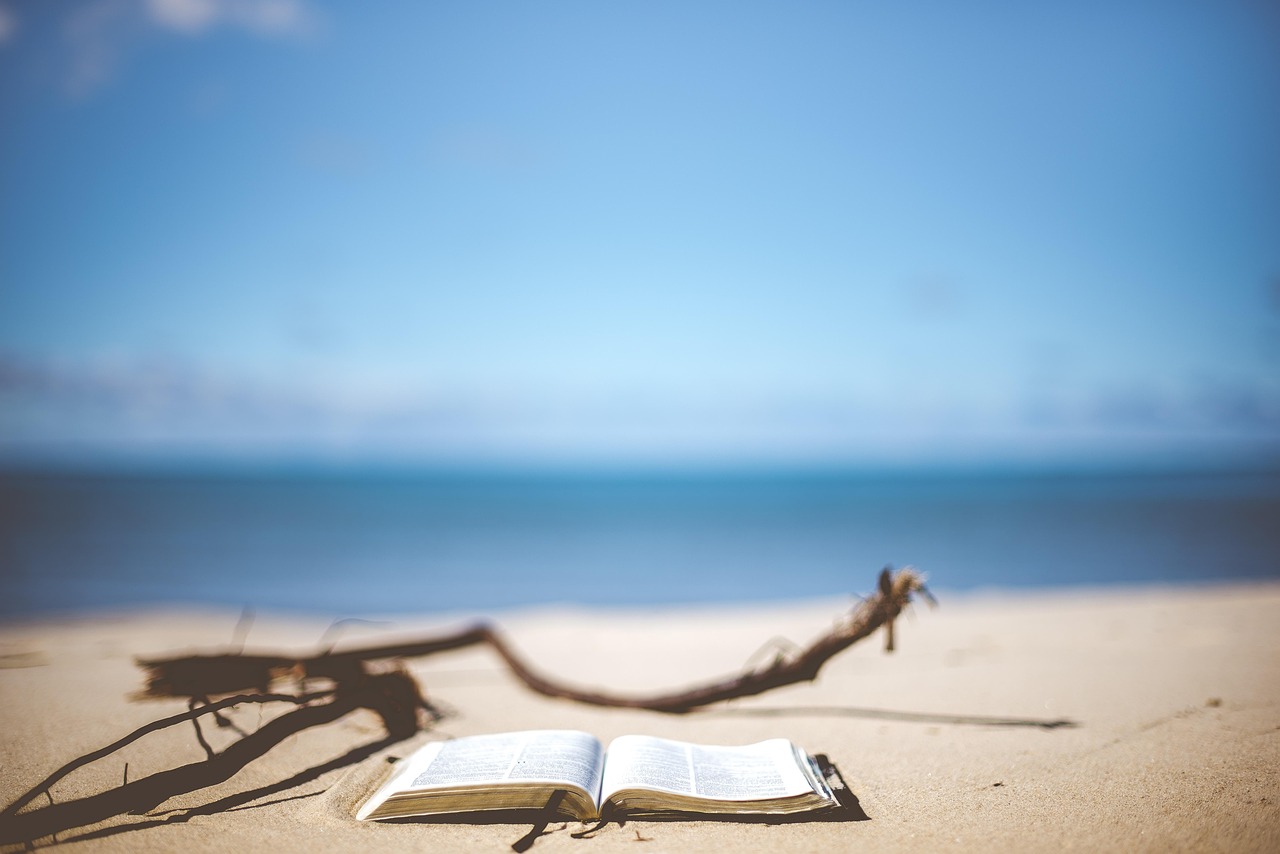


コメント