ビジネスにおける電話は、今なお重要なコミュニケーション手段のひとつです。メールやチャットが普及している現代でも、電話は相手の声を直接届けるため、スピード感や信頼性を重視する場面で頻繁に活用されています。特に初めて接点を持つ顧客や取引先にとっては、電話応対がその企業や担当者に対する最初の印象となることが多いです。
電話は顔が見えない分、相手が受け取る情報は「声のトーン」「言葉遣い」「応対の速さ」といった要素に限られます。丁寧で適切な対応ができれば「信頼できる相手」という印象を与えることができますが、逆に雑な応対をしてしまうと一瞬で信頼を損ねることにもつながります。そのため、電話マナーは単なる形式的なルールではなく、社内外で信頼を築くための重要なスキルなのです。
基本の電話マナーを押さえる
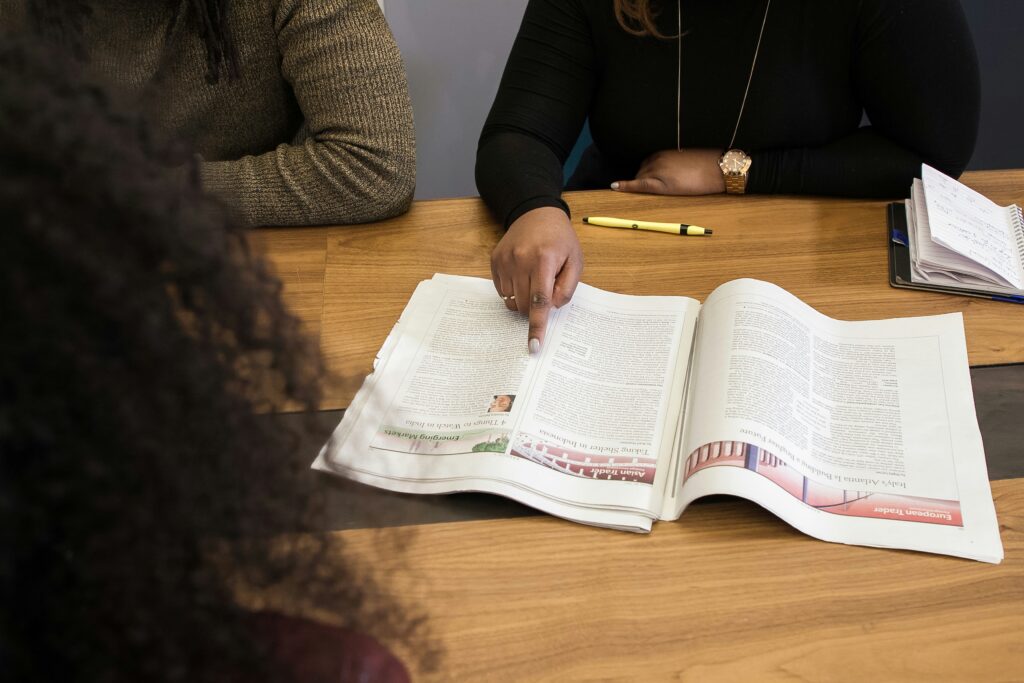
1. 電話を受ける際の第一声と名乗り方
電話を受けたときの第一声は、そのまま会社の印象を決定づけます。基本は「お電話ありがとうございます。○○株式会社でございます」と明るくはっきり名乗ることです。声のトーンは普段より少し高めを意識し、ハキハキと発音することで信頼感が増します。
また、相手の名前を聞き取った際には「○○様でいらっしゃいますね」と復唱することで、聞き間違いを防ぐと同時に丁寧さを示せます。
2. 電話をかける際の基本的な流れ
電話をかける場合は、まず「いつもお世話になっております。○○株式会社の△△でございます」と自分の所属と名前を名乗ります。次に「ただいまお時間よろしいでしょうか」と相手の状況を確認してから本題に入ることが望ましいです。いきなり要件を伝えるのではなく、相手に配慮を示すことで円滑なやり取りにつながります。
3. 敬語・クッション言葉の使い方
電話応対では敬語表現が欠かせません。特にクッション言葉を適切に使うことで、相手に柔らかい印象を与えることができます。
- 「恐れ入りますが、○○をお願いできますでしょうか」
- 「お手数をおかけいたしますが、ご確認いただけますでしょうか」
- 「差し支えなければ、□□についてお伺いしてもよろしいでしょうか」
こうした表現を使うと依頼や確認も円滑に進みます。
4. メモと復唱で正確さを担保するポイント
電話でのやり取りは記録が残らないため、聞き間違いや伝達漏れが起きやすいものです。そのため、必ずメモを取り、日時や数字、固有名詞は復唱して確認することが大切です。「○月○日の△時にお伺いするということでよろしいでしょうか」と復唱するだけで、正確さが格段に高まります。
応用編:信頼を深めるための実践テクニック

1. 社内での電話応対と社外対応の違い
社内の電話では、同僚や上司とのやり取りが中心となります。形式的な敬語は必要ですが、過度に堅苦しくなる必要はありません。一方で、社外の相手との電話では、言葉遣いや声のトーンに一層の注意が求められます。社外対応では「会社を代表している」という意識を持ち、常に丁寧さを心がけることが重要です。
2. クレームやトラブル時に落ち着いて対応する方法
顧客や取引先からのクレームを受けた場合、まずは「ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございません」と謝意を伝えることが第一です。相手の話を最後まで遮らずに聞き、共感を示すことで感情を和らげることができます。その後「確認のうえ、折り返しご連絡いたします」と伝え、冷静に対応する姿勢を見せることが信頼回復につながります。
3. 相手に安心感を与える声のトーンと間の取り方
電話では声だけが頼りです。落ち着いたトーンでゆっくり話すと、聞き手に安心感を与えます。逆に早口や単調な声は、焦りや不誠実な印象を与えてしまいます。また、適度に「間」を取ることも大切です。「えっと」「あのー」と filler words を挟むのではなく、一呼吸置くことで落ち着きが感じられます。
4. 相手の状況に合わせた言葉選びの工夫
例えば、忙しそうな相手には「お急ぎのところ恐れ入ります」と前置きするだけで印象が和らぎます。相手が不安を抱えている場合には「ご安心ください。こちらで責任を持って対応いたします」といった言葉を添えると安心感が伝わります。状況に応じた言葉選びは、相手の気持ちを尊重する姿勢を示し、信頼を深める効果があります。
まとめ

電話応対は、一度のやり取りで相手に強い印象を与える大切な機会です。信頼される応対を実現するためには、基本を徹底することに加えて、状況に応じた応用力も求められます。
- 第一声は明るくはっきり名乗る
- 相手の状況に配慮して会話を進める
- クッション言葉や敬語を正しく使う
- メモと復唱で正確さを担保する
- クレーム時には冷静さと誠意を示す
これらを日常的に実践し習慣化することで、社内外からの信頼を得られるようになります。電話応対は単なる連絡手段ではなく、信頼を築くチャンスです。基本から応用までを意識して取り組むことで、ビジネス全体に良い影響をもたらすことができるでしょう。



コメント