社会人として最初に任される業務のひとつが電話対応です。メールやチャットが主流となった現代においても、電話は即時性があり、相手の声を直接届けられる手段として重要な役割を担っています。しかし、顔が見えない状況でのやり取りに不安を感じる新人は多く、適切な対応ができるかどうかが自信と信頼に直結します。
電話対応は、単なる連絡手段ではなく「会社の第一印象を決める窓口」としての意味を持っています。新人の応対ひとつで、企業全体の印象が左右されるといっても過言ではありません。そのため、まずは基本となるマナーをしっかりと理解し、実践できるようにすることが大切です。本記事では、新人が最初に覚えておくべき電話対応の基本ポイントを10個にまとめてご紹介いたします。
電話対応マナーの基本ポイント10選

1. 明るい第一声で名乗る
電話を受けたときの第一声は、相手の印象を大きく左右します。「お電話ありがとうございます。○○株式会社でございます」と、会社名を明確に伝えましょう。声は普段より少し高めに、はっきりとしたトーンを意識することが大切です。
2. 丁寧な敬語を使う
敬語は信頼関係を築くための基本です。「了解しました」ではなく「承知いたしました」、「ちょっと待ってください」ではなく「少々お待ちいただけますでしょうか」といった正しい言葉遣いを習慣化しましょう。
3. メモを必ず取る
電話のやり取りは記録が残りにくいため、必ずメモを取りましょう。相手の名前、連絡先、日時、用件など、後から確認が必要になる情報を残しておくことは信頼性につながります。
4. 復唱で正確さを確認する
情報を正しく伝達するためには復唱が欠かせません。「○月○日の△時にお伺いするということでよろしいでしょうか」と確認することで、聞き間違いを防ぐことができます。
5. クッション言葉を活用する
依頼やお願いをするときには、いきなり本題に入らずクッション言葉を添えることで柔らかい印象を与えられます。
- 「恐れ入りますが」
- 「お手数をおかけいたしますが」
- 「差し支えなければ」
これらの表現を活用すると、相手への配慮が伝わります。
6. 相手の話を最後まで聞く
相手の話を遮らず、最後まで聞く姿勢が重要です。適度に「はい」「承知いたしました」と相槌を入れることで、きちんと話を聞いているという安心感を与えられます。
7. 保留・取次ぎの正しい言い方
担当者へ取り次ぐ場合には「恐れ入りますが、△△におつなぎいたしますので、少々お待ちくださいませ」と伝えます。保留時は「保留にさせていただきます」と断りを入れることで、相手に不安を与えません。
8. 折り返しの約束は具体的に伝える
担当者が不在の場合は「戻り次第、折り返しご連絡いたします」と伝え、可能であれば「本日中に」や「△時頃までに」と具体的な目安を示すと相手に安心感を与えられます。
9. クレーム対応ではまず謝意を示す
相手が不満を抱えている場合には、まず「ご不快な思いをおかけし申し訳ございません」と謝意を伝えることが第一歩です。その上で、事実確認と今後の対応を誠実に説明することで、信頼回復につながります。
10. 終話時に感謝を伝える
電話を終える際には「本日はお電話いただきありがとうございました。失礼いたします」と感謝の言葉を添えましょう。最後の一言が全体の印象を締めくくるため、丁寧に伝えることが大切です。
実践に役立つ工夫と練習法
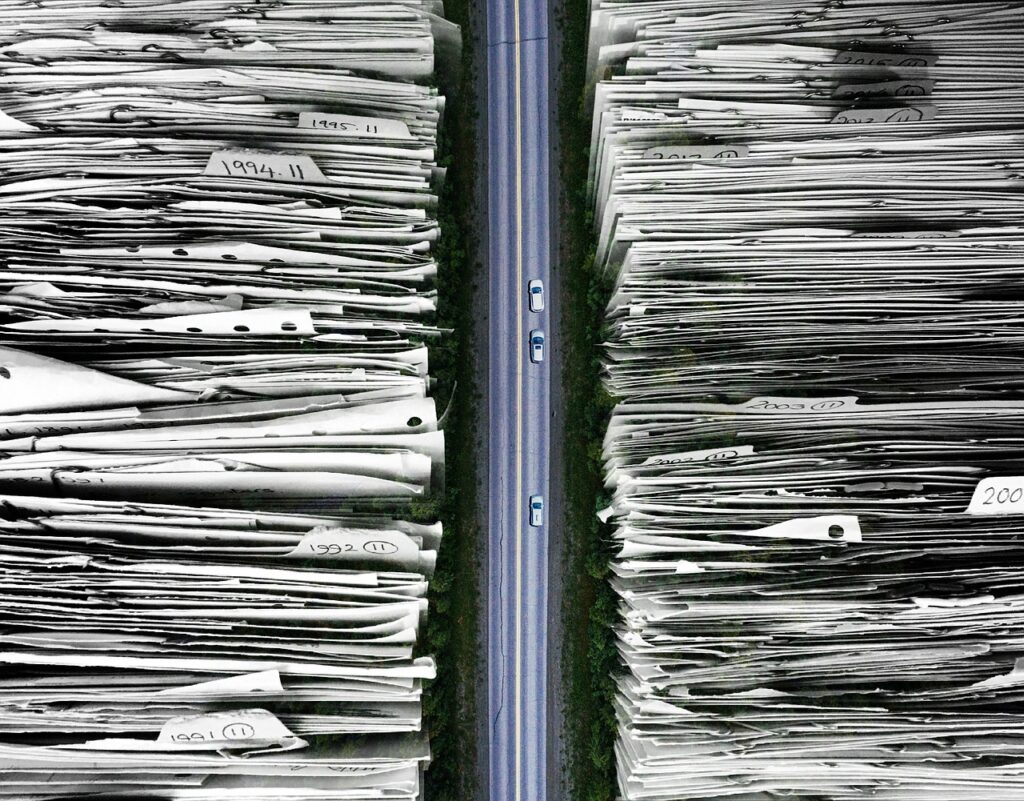
ロールプレイで場数を踏む
同僚や上司とロールプレイを行い、実際の場面を想定して練習することで自信がつきます。特に新人時代は場数を踏むことが大きな成長につながります。
録音して自分の声を確認する
自分の声を録音して聞き返すと、話し方の癖や改善点が分かります。「声が小さい」「敬語が不自然」など、客観的に気づけることが多いです。
定型フレーズを暗記しておく
よく使うフレーズを事前に暗記しておくと、焦ったときにも自然に言葉が出てきます。特に「名乗り」「保留」「折り返し依頼」などの基本表現は繰り返し練習しておきましょう。
不安を軽減するための呼吸法・発声練習
緊張を和らげるためには、深呼吸や発声練習が効果的です。腹式呼吸を意識すると声が安定し、落ち着いた印象を与えられます。
まとめ

電話対応は、新人にとって最初の大きな試練であり、同時に信頼を築くチャンスでもあります。最初は緊張や失敗がつきものですが、基本のマナーを意識し、繰り返し実践することで確実に上達します。
- 明るくはっきりとした第一声
- 丁寧な敬語表現
- メモと復唱による正確さ
- クッション言葉や傾聴姿勢で相手に配慮
- 終話時の感謝の言葉
これらの基本を日常の中で習慣化することで、自然と自信がつき、社内外から信頼される存在へと成長できます。電話対応は単なる事務作業ではなく、信頼を築く第一歩です。今日からひとつずつ意識して取り入れ、安心感を与える応対を実践していきましょう。



コメント