社会人として働き始めると、まず最初に任されることの多い業務が電話対応です。しかし、メールやチャットが主流となった時代に育った新人にとって、電話は「相手の顔が見えない」「即時に対応が求められる」という点で特に難易度が高いと感じられる場面です。
緊張や経験不足から言葉に詰まってしまったり、敬語の誤用をしてしまったりすることは珍しくありません。また、想定外の質問やクレームに直面したときに慌ててしまい、不適切な言葉遣いをしてしまうこともあります。
しかし、失敗は成長の糧です。正しい言葉遣いや対応方法を学び、繰り返し実践することで、誰でも自信を持った電話対応ができるようになります。本記事では、新人が陥りやすい電話対応での失敗例を整理し、それに対する正しい言い方と改善策をご紹介いたします。
新人が失敗しやすい電話対応の例

1. 名乗りが不明瞭で聞き返される
電話を受けた際に「はい、○○です」と小さな声で答えると、相手に会社名や部署が伝わらず、不安を与えてしまいます。第一声が曖昧だと、その後の会話も信頼性を欠く印象になりがちです。
2. 「了解しました」「ご苦労様です」など誤った敬語を使う
新人が特に失敗しやすいのが敬語の誤用です。「了解しました」は目上の人に対しては失礼にあたるため、「承知いたしました」と言い換える必要があります。また「ご苦労様です」は上から目線の表現になりやすいため、社外の相手には「お疲れ様でございます」と伝えるのが適切です。
3. メモを取らずに内容を忘れる
電話は記録が残らないため、記憶に頼ると要件を忘れてしまう危険があります。特に名前や日時、数字などは誤りが生じやすく、伝達ミスにつながります。
4. 保留や取次ぎの対応が不適切
「ちょっと待ってください」と急に電話を切るような対応は相手に不快感を与えます。また、担当者が不在の場合に「いません」とだけ伝えるのも不適切です。配慮の欠けた言い方は、会社全体の印象を下げてしまいます。
5. クレーム時に慌てて言葉を間違える
クレーム対応では焦りから「分かりません」「できません」と即答してしまうことがあります。こうした言い方は冷たい印象を与え、相手の怒りを増幅させる恐れがあります。
正しい言い方と改善のポイント
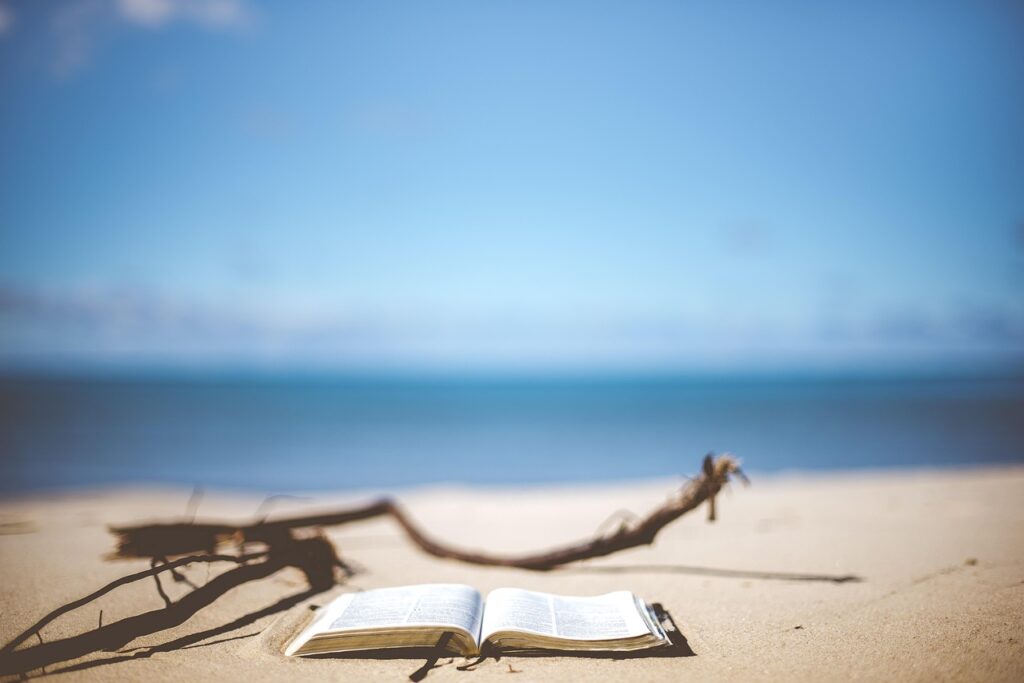
1. 第一声は明るくはっきりと名乗る
電話を受けたときは「お電話ありがとうございます。○○株式会社でございます」と明確に伝えましょう。声を少し高めにして明るく話すと、相手に安心感を与えられます。かけるときも「いつもお世話になっております。○○株式会社の△△でございます」と所属と名前をはっきり名乗ることが基本です。
2. 正しい敬語を習慣化する
- 「了解しました」→「承知いたしました」
- 「ご苦労様です」→「お疲れ様でございます」
- 「ちょっと待ってください」→「少々お待ちいただけますでしょうか」
こうした言い換えを日常的に練習しておくと、自然に正しい敬語が使えるようになります。
3. 復唱とメモで正確性を担保する
電話では必ずメモを取り、要点を整理しましょう。さらに「○月○日の△時にお伺いするということでよろしいでしょうか」と復唱することで、誤解を防ぎ正確に伝達できます。復唱は相手に対して「きちんと理解している」という安心感を与える効果もあります。
4. 保留や折り返し依頼の正しいフレーズ
保留するときは「恐れ入りますが、確認いたしますので少々お待ちくださいませ」と伝え、保留の時間が長くなる場合は一度電話口に戻り「お待たせして申し訳ございません。もう少々お時間をいただけますでしょうか」と声をかけましょう。
担当者が不在の場合は「ただいま席を外しております。戻り次第、折り返しご連絡いたします」と伝えるのが適切です。さらに「ご都合の良い時間帯をお伺いしてもよろしいでしょうか」と添えると、より丁寧な印象になります。
5. クレーム対応時の謝罪と確認の仕方
クレームに対しては、まず「ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪を伝えましょう。その後、「ただいまの件について確認のうえ、折り返しご連絡いたします」と冷静に対応します。感情的にならず、共感と誠意を示すことが信頼回復の第一歩です。
まとめ

新人が電話対応で失敗してしまうのは自然なことです。大切なのは失敗をそのままにせず、正しい言い方を学んで改善につなげることです。
- 明るい第一声で安心感を与える
- 正しい敬語を意識して使う
- メモと復唱で正確さを確保する
- 保留や折り返し時に配慮のある言葉を使う
- クレーム対応では謝意と誠実さを示す
これらを繰り返し実践することで、自然と正しい言葉遣いが身につき、電話対応に自信が持てるようになります。新人時代の失敗は成長のきっかけであり、習慣化された正しいマナーがやがて信頼へとつながります。電話対応を単なる事務作業ではなく「信頼構築の場」として意識することが、ビジネスパーソンとしての大きな成長につながるのです。
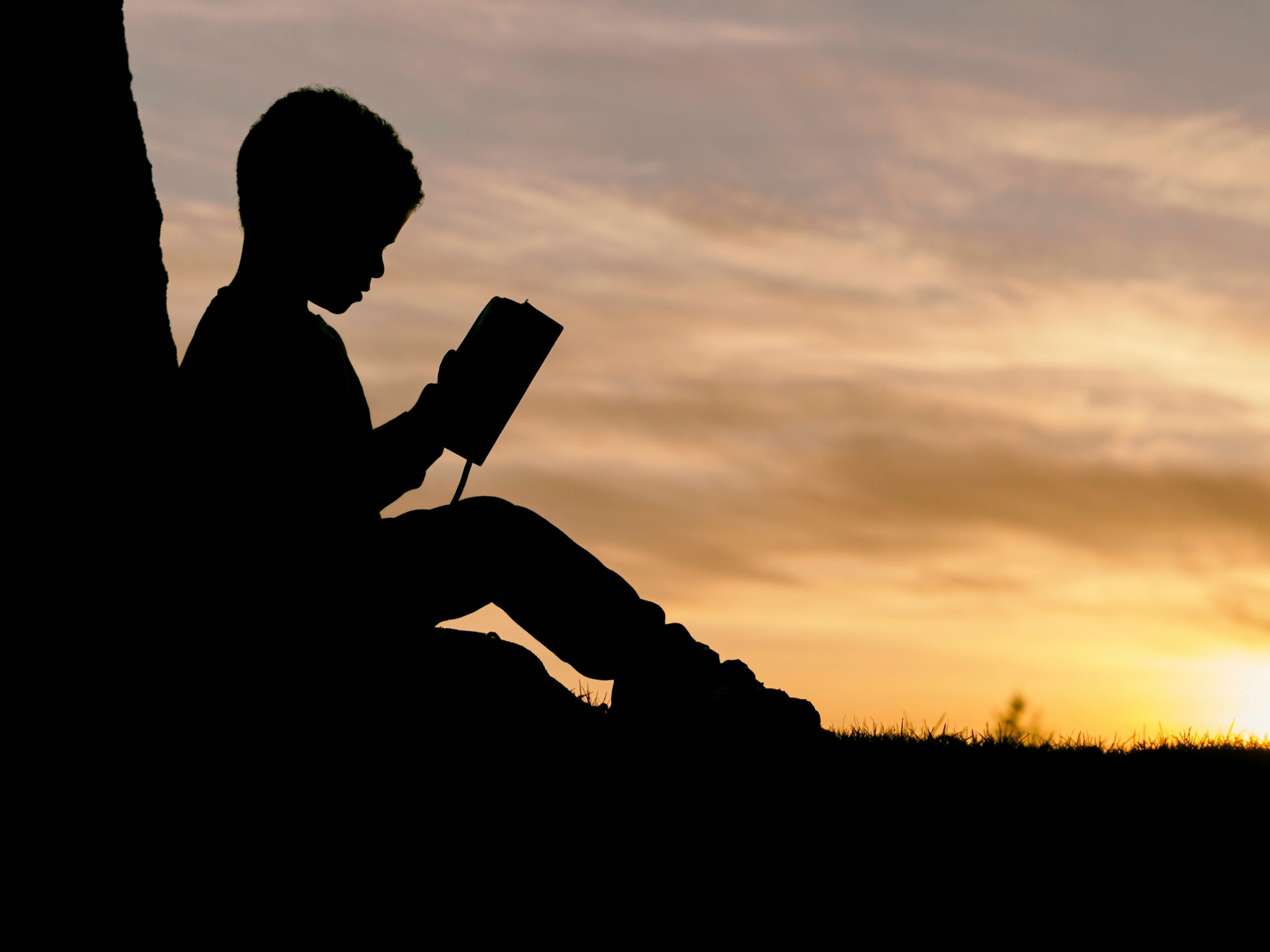


コメント