ビジネスにおいて電話は今なお重要なコミュニケーション手段のひとつです。メールやチャットが普及した現在でも、電話は迅速かつ直接的なやり取りができるため、取引や顧客対応の場面では欠かせません。
しかし、電話は相手の顔が見えないため、声のトーンや言葉遣いだけで印象が決まります。そのため、適切な敬語を使えるかどうかが信頼の獲得に大きく影響します。逆に誤った敬語や不適切な言い回しをしてしまうと、「失礼な人」「不慣れな対応」という印象を与えてしまう可能性があります。
本記事では、電話でよく使う正しい敬語表現を一覧で整理するとともに、やってしまいがちなNG例とその言い換えを解説いたします。これらを理解して習慣化することで、安心感と信頼を与える電話応対が可能になります。
電話でよく使う正しい敬語表現一覧

1. 受電・名乗り・あいさつの場面
- 電話を受けたとき:「お電話ありがとうございます。○○株式会社でございます」
- 名乗るとき:「○○株式会社の△△と申します」
- 挨拶を添えるとき:「いつもお世話になっております」
第一声で明るくはっきりと名乗ることで、相手に安心感を与えられます。
2. 取次ぎ・保留・折り返し依頼の場面
- 担当者に取り次ぐとき:「恐れ入りますが、△△におつなぎいたします。少々お待ちいただけますでしょうか」
- 保留にする場合:「確認のため保留にさせていただきます。少々お待ちくださいませ」
- 折り返しを依頼するとき:「恐れ入りますが、折り返しご連絡いただけますでしょうか」
- こちらから折り返す場合:「担当者が戻り次第、こちらからご連絡差し上げます」
相手に配慮した表現を添えることで、不快感を与えずに対応できます。
3. 確認・復唱・感謝の表現
- 確認するとき:「念のため、復唱させていただきます」
- 日時を確認する場合:「○月○日の△時ということでお間違いないでしょうか」
- 感謝を伝えるとき:「ご連絡いただきありがとうございます」
- 会話の締め:「本日はお電話いただき誠にありがとうございました」
正確さと丁寧さを兼ね備えた言い方は、信頼を高めます。
4. クレームや謝罪対応での丁寧な言い回し
- 謝罪するとき:「ご不快な思いをおかけし、誠に申し訳ございません」
- 共感を示す場合:「そのように感じられるのもごもっともでございます」
- 再確認をする場合:「ただいまの件、確認のうえ折り返しご連絡いたします」
- 感謝で締める場合:「ご指摘いただきありがとうございます。今後の改善に活かしてまいります」
誠意ある表現を選ぶことで、トラブルを信頼回復の機会に変えることができます。
NG例と正しい言い換えフレーズ

電話応対では、無意識に使ってしまいがちな表現が存在します。以下は特によくあるNG例と正しい言い換えです。
- 「了解しました」 → 「承知いたしました」「かしこまりました」
- 「ご苦労様です」 → 「お疲れ様でございます」
- 「ちょっと待ってください」 → 「少々お待ちいただけますでしょうか」
- 「いません」 → 「ただいま席を外しております」
- 「誰ですか?」 → 「どちら様でいらっしゃいますでしょうか」
- 「忘れました」 → 「確認不足で申し訳ございません。すぐに調べてご連絡いたします」
言葉のニュアンスひとつで相手が受け取る印象は大きく変わります。否定的・断定的な表現を避け、柔らかく丁寧な言い回しを心がけることが信頼獲得につながります。
まとめ

電話での敬語は、相手の信頼を得るための大切な要素です。正しい言葉遣いを習慣化することで、どんな場面でも落ち着いて対応できるようになります。
- 受電・名乗り・あいさつ:第一声を明るく丁寧に
- 取次ぎ・保留・折り返し:配慮ある言葉を添える
- 確認・復唱・感謝:正確さと丁寧さを両立
- クレーム対応:謝罪・共感・確認を誠実に
また、NG例を知り正しい言い換えを習慣化することで、自然と洗練された会話ができるようになります。電話は単なる業務ツールではなく、信頼を築く第一歩です。日常的に敬語を意識して磨き、安心感を与える電話応対を実践していきましょう。
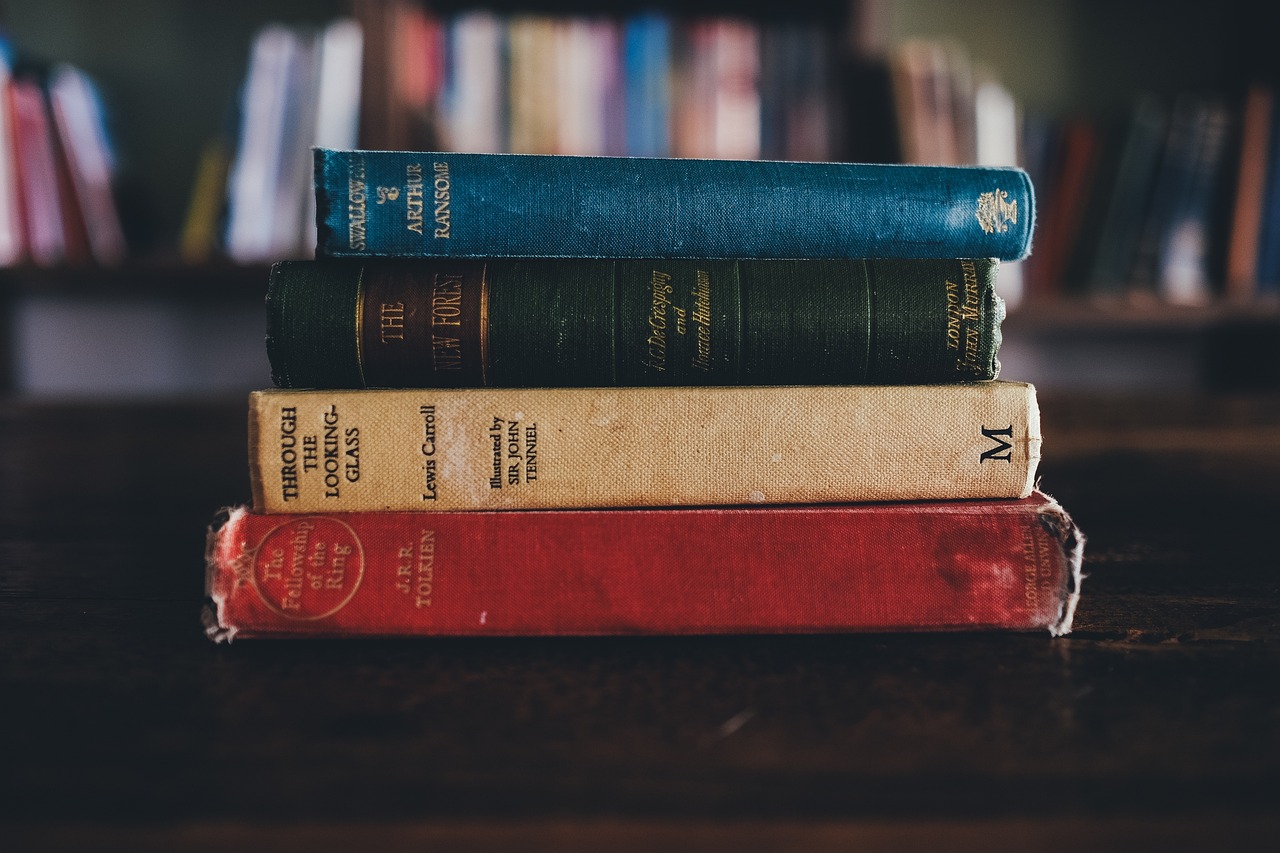


コメント